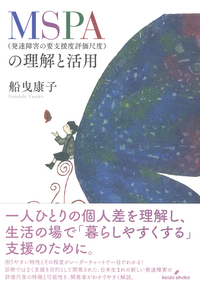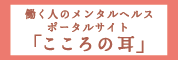2009年03月17日
アサーショントレーニングin小学校
今年もTTで小5の生徒達に「アサーショントレーニング」を行いました。
第1回目は「アサーションを知ろう!」
自己表現の三つのタイプを説明し、アサーションとはどんな事なのかを説明しました。
毎度お馴染みのドラえもんで…
「非主張的」なのび太クン、「攻撃的」なジャイアン、「アサーティブ」なしずかちゃん、できすぎくんはしっかり理解できたようでした。
振り返りでは、自分が相手によって自己表現が変化している事に気がついていた子が多かったです。
今時の小学生は…
友達には「アサーティブ」、弟や妹には「攻撃的」、お母さんには「非主張的」な傾向にあるようです。
アサーティブの「自分も相手も大切に」では、相手への配慮を意識する子が多かったので、「自分を大切に」がまず大事なことを強調しました。
第2回目は「失敗しちゃったらどうする?」
自分の発言で相手に不愉快な思いをさせてしまった時にどうするのか…
モデルを提示して、ロールプレイで体験してもらいました。
攻撃的になるのはやりやすいようでした。
一生懸命アサーティブに自己表現しようと努力する姿が印象的でした。
アサーティブな会話には工夫が必要なことを説明しました。
「アイメッセージ」と「自分の気持ちにウソをつかない表現」、「言葉の意味を具体的に、適切に伝えること」について話しました。
聞いている時の反応があまりなかったので心配でしたが、振り返りではしっかり伝わっていたことが分かりました。
そして第3回目「さわやかさんで言ってみよう!」
このモデルは「子どものためのアサーショングループワーク」にあります。
まず、「さわやか」とはどんなことかでつまずきました。
炭酸飲料を飲んだ感じとか、シャワーやお風呂に入った後とか…
説明して見ましたが…
今一の反応でした。
辞書によると「さっぱりとして気持ちが良い」とか「はっきりしていて聞きやすい」と言うことだと説明しました。
四こまマンガを題材にアサーションのトレーニングです。
グループで意見をまとめて発表する方法で行いました。
たった3回の授業なのですか…
ビックリです。
全てのグループがアサーティブに意見がまとまりました。
多少未熟な部分はいなめませんが、子どもの素晴らしさがヒシヒシト感じられました。
校長先生にも授業を参観していただきました。
その後の打ち合わせでは、「先生方に是非アサーショントレーニングを!」と提案させていただきました。
先生がモデルとなると子どもたちも日常でアサーティブになりやすいからです。
大人の研修と異なり、子どもに理解してもらうために言葉や表現に工夫が必要です。
学校の先生達の苦労も感じながらの素晴らしい体験となりました。
第1回目は「アサーションを知ろう!」
自己表現の三つのタイプを説明し、アサーションとはどんな事なのかを説明しました。
毎度お馴染みのドラえもんで…
「非主張的」なのび太クン、「攻撃的」なジャイアン、「アサーティブ」なしずかちゃん、できすぎくんはしっかり理解できたようでした。
振り返りでは、自分が相手によって自己表現が変化している事に気がついていた子が多かったです。
今時の小学生は…
友達には「アサーティブ」、弟や妹には「攻撃的」、お母さんには「非主張的」な傾向にあるようです。
アサーティブの「自分も相手も大切に」では、相手への配慮を意識する子が多かったので、「自分を大切に」がまず大事なことを強調しました。
第2回目は「失敗しちゃったらどうする?」
自分の発言で相手に不愉快な思いをさせてしまった時にどうするのか…
モデルを提示して、ロールプレイで体験してもらいました。
攻撃的になるのはやりやすいようでした。
一生懸命アサーティブに自己表現しようと努力する姿が印象的でした。
アサーティブな会話には工夫が必要なことを説明しました。
「アイメッセージ」と「自分の気持ちにウソをつかない表現」、「言葉の意味を具体的に、適切に伝えること」について話しました。
聞いている時の反応があまりなかったので心配でしたが、振り返りではしっかり伝わっていたことが分かりました。
そして第3回目「さわやかさんで言ってみよう!」
このモデルは「子どものためのアサーショングループワーク」にあります。
まず、「さわやか」とはどんなことかでつまずきました。
炭酸飲料を飲んだ感じとか、シャワーやお風呂に入った後とか…
説明して見ましたが…
今一の反応でした。
辞書によると「さっぱりとして気持ちが良い」とか「はっきりしていて聞きやすい」と言うことだと説明しました。
四こまマンガを題材にアサーションのトレーニングです。
グループで意見をまとめて発表する方法で行いました。
たった3回の授業なのですか…
ビックリです。
全てのグループがアサーティブに意見がまとまりました。
多少未熟な部分はいなめませんが、子どもの素晴らしさがヒシヒシト感じられました。
校長先生にも授業を参観していただきました。
その後の打ち合わせでは、「先生方に是非アサーショントレーニングを!」と提案させていただきました。
先生がモデルとなると子どもたちも日常でアサーティブになりやすいからです。
大人の研修と異なり、子どもに理解してもらうために言葉や表現に工夫が必要です。
学校の先生達の苦労も感じながらの素晴らしい体験となりました。
Posted by Mako Takabayashi at 01:00│Comments(0)
│学校