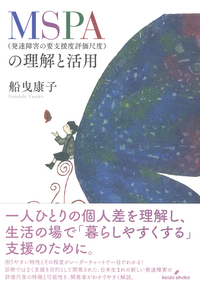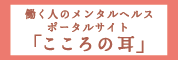2012年09月01日
いじめとスクールカウンセラー
文科省がいじめ対策でスクールカウンセラーとソーシャルワーカーを増やす事に予算を付けた。
そこで問題なのは、いじめ問題に即決しているのかだ。
すでに現場を離れて数年たっているので的外れかもしれないが、私見を述べてみたい。
スクールカウンセラーは個人の力量で、あるいは校長の独裁で運営されている。
あまりにもまちまちで、様々になっていて、体系的でないし、レベルも運営も大きく異なってしまっている。
予算をつけて人を増やしたからと言って効果が望めるのかが疑問だ。
学校と言う現場は公務員的でありながらも、熱意や意欲のある教師たちがまだまだいる。
その教師たちが疲弊していて、今の子どもたちの問題に巻き込まれてしまっていると私は感じていた。
先生は勉強を教える人であって、聖人君子ではない。
スクールカウンセラーはあくまで部外者で、仲間ではなく、先生にとっての先生扱いになりがちだ。
連携したくても、様々な教師たちの個人的見解によって敵にもなり味方にもなる。
校長が権限を発揮していて、教師たちとも信頼関係があり、かつスクールカウンセラーや支援員も対子どもにとっては対等だと認識しつつ、活用しようとしていなければ何の役にも立てない。
果たしてそんな校長が何人いるのだろうか…
本当に少ないのが現実だ。
それは、今回の大津のいじめ問題にも如実に表れていたと思う。
だからと言って、私は校長のせいだと言っているのではない。
スクールカウンセラーやソーシャルワーカーが現場にとってお客様状態である限りは何の効用も望めないと言うことだ。
教育に教師以外の先生は必要だ。
何でも教師がになっていては、教師がつぶれてしまう。
だからと言って今のスクールカウンセラーやソーシャルワーカーの制度は有効なのか?
そこも検証しなければ、本来のいじめ対策では決して機能しないと私は断言できる。
そこで問題なのは、いじめ問題に即決しているのかだ。
すでに現場を離れて数年たっているので的外れかもしれないが、私見を述べてみたい。
スクールカウンセラーは個人の力量で、あるいは校長の独裁で運営されている。
あまりにもまちまちで、様々になっていて、体系的でないし、レベルも運営も大きく異なってしまっている。
予算をつけて人を増やしたからと言って効果が望めるのかが疑問だ。
学校と言う現場は公務員的でありながらも、熱意や意欲のある教師たちがまだまだいる。
その教師たちが疲弊していて、今の子どもたちの問題に巻き込まれてしまっていると私は感じていた。
先生は勉強を教える人であって、聖人君子ではない。
スクールカウンセラーはあくまで部外者で、仲間ではなく、先生にとっての先生扱いになりがちだ。
連携したくても、様々な教師たちの個人的見解によって敵にもなり味方にもなる。
校長が権限を発揮していて、教師たちとも信頼関係があり、かつスクールカウンセラーや支援員も対子どもにとっては対等だと認識しつつ、活用しようとしていなければ何の役にも立てない。
果たしてそんな校長が何人いるのだろうか…
本当に少ないのが現実だ。
それは、今回の大津のいじめ問題にも如実に表れていたと思う。
だからと言って、私は校長のせいだと言っているのではない。
スクールカウンセラーやソーシャルワーカーが現場にとってお客様状態である限りは何の効用も望めないと言うことだ。
教育に教師以外の先生は必要だ。
何でも教師がになっていては、教師がつぶれてしまう。
だからと言って今のスクールカウンセラーやソーシャルワーカーの制度は有効なのか?
そこも検証しなければ、本来のいじめ対策では決して機能しないと私は断言できる。