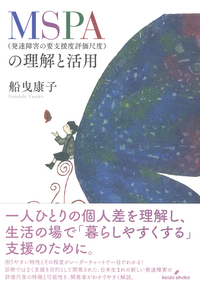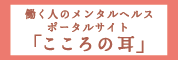2017年10月31日
セロトニンとメラトニン

うつ状態では脳内物質が影響していることが分かってきました。中でもセロトニンとメラトニンについてまとめてみました。
 セロトニンとは
セロトニンとはセロトニンとは、トリプトファンの代謝過程で生成されるホルモン作用や神経伝達作用を示す生体化学情報伝達物質。人体には、総量で約10mg程度存在しており90%は小腸の粘膜にあるクロム親和細胞(EC細胞とも呼ばれる)内にあります。小腸のエンテロクロマフィン細胞はセロトニンを合成し、その一部総量の約8%は血小板に取り込まれます。脳内では中脳と延髄の間にある神経核「ほうせん核」から1秒に2回の一定リズムで分泌され、約2%が中枢神経系に存在しています。神経終末(シナプス)に放出されたセロトニンの約8割は元の神経終末に再び取り込まれ、2割が酸素によって捨てられます。脳内のセロトニンは他の神経伝達物質であるドーパミン(喜び、快楽)、ノルアドレナリン(恐れ、驚き)の活性を抑制し、精神を安定させる作用があります。
 なぜセロトニンのリサイクル機能が低下するのか
なぜセロトニンのリサイクル機能が低下するのか慢性的にストレスを感じ続け、悩み続けると、糖質コルチコイドというストレス物質がどんどん増えていきます。糖質コルチコイドが増え続けると、セロトニン再取り込み口を埋め、セロトニンを吸えなくなってしまうのです。そうすると、酸素によって捨てられるセロトニンが増えるのにもかかわらず、ほう線核から供給されるセロトニン量は相変わらずわずかなまま。こうなると糖質コルチコイドに邪魔をされ、ついに再取り込み口自体も消滅してしまいます。そして慢性的なセロトニン不足となってしまうのです。
 メラトニンとは
メラトニンとはメラトニンとは、脳の松果体で生産され分泌されるホルモン。トリプトファンからセロトニンを経て合成されます。メラトニンの合成は昼間(明期)に抑制され、夜間(暗期)は促進されるというように明暗サイクルと関連しています。このことからメラトニンは、睡眠・覚醒周期などの生体の日内リズムや内分泌系を制御する働きをもつと考えられています。
 セロトニンとメラトニンのしくみ
セロトニンとメラトニンのしくみセロトニンはトリプトファン(必須アミノ酸)によって体内で生成されます。そしてさらに合成されメラトニンとなるのです。セロトニンは起床時に太陽光を浴びることで増加します。起床時で増加したセロトニンはその後減少し14~16時間後にメラトニンに変化します。メラトニンは午前2時ごろピークを迎え徐々に減少していきます。

 ビタミンB6・ナイアシン・マグネシウムは、セロトニンを生成するために必要です。
ビタミンB6・ナイアシン・マグネシウムは、セロトニンを生成するために必要です。 ブドウ糖は、トリプトファンがほうせん核に入るのを助ける働きがあります。
ブドウ糖は、トリプトファンがほうせん核に入るのを助ける働きがあります。 トリプトファンは体内で合成できないため、食べ物で摂取する必要があります。
トリプトファンは体内で合成できないため、食べ物で摂取する必要があります。 セロトニンとメラトニンのための食べ物
セロトニンとメラトニンのための食べ物 トリプトファンを多く含む食品
トリプトファンを多く含む食品オートミール、ナッツ類(ごま、アーモンド、落花生、くるみ、カシューナッツ)、あずき、大豆製品(きな粉、凍り豆腐、納豆)、魚類に多い(特に、しらす干し、たらこ、のり、わかめ、かつお、まぐろ)、肉類に多い(特にレバー)乳製品(牛乳、チーズ)など
 ビタミンB6を多く含む食品
ビタミンB6を多く含む食品魚(特にまぐろ、さんま、さけ、さば)、肉(特にレバー、豚肉)、豆類、卵、バナナ、サツマイモ
 ナイアシンを多く含む食品
ナイアシンを多く含む食品魚(特にかつお、まぐろ)、肉(特にレバー、豚肉)、落花生など
 マグネシウムを多く含む食品
マグネシウムを多く含む食品海藻や魚介類、豆類、ナッツ類など
 セロトニン活性化のために
セロトニン活性化のために 太陽光を浴びる (2500ルクス以上の光が必要)
太陽光を浴びる (2500ルクス以上の光が必要)※ほう線核は、目の網膜から光の信号が5分以上伝わると活動が活発化する。
 適度なリズム運動をする(朝15~30分間くらい) <例>ウォーキング
適度なリズム運動をする(朝15~30分間くらい) <例>ウォーキング※ウォーキングを始めると、15分程度でβエンドルフィンが出てきて、その後続いてセロトニンが分泌される。
 「首回し」をする。
「首回し」をする。※首を動かすと、大量の電気信号が伝わり、脳幹の神経核が活性化し、セロトニンの生成・分泌を増やしてくれる。
 主にほうせん核に働きかけ、セロトニンの分泌を促してくれる香りは、リラックスの代表とも呼ばれるラベンダー。その他、ローマンカモミール、ラベンダー、マジョラム、ネロリ等
主にほうせん核に働きかけ、セロトニンの分泌を促してくれる香りは、リラックスの代表とも呼ばれるラベンダー。その他、ローマンカモミール、ラベンダー、マジョラム、ネロリ等Posted by Mako Takabayashi at 22:39│Comments(0)
│カウンセリング