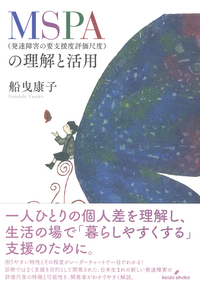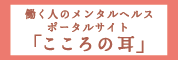2012年07月01日
ロバート・クロニンジャーの「気質と性格の7次元モデル」
性格とはどんなものなのでしょう…
心理学では色々な性格論があります。
その一つを紹介します。
ロバート・クロニンジャーの「気質と性格の7次元モデル」
ロバート・クロニンジャー(Robert Cloninger)は1944年生まれの精神科医で遺伝学者。
1996年にネズミの行動パターンの研究から構築された「気質と性格の7次元モデル」を提唱しました。
遺伝子や脳機能と「性格」を関連付けた最新の理論です。
パーソナリティ形成では遺伝的要素も強い影響を与えると提唱し、遺伝子構造が脳内の神経伝達物質、とりわけ受容体の働きや個数に影響を与え、行動をも左右するとしました。
特徴
 学習理論に基づいている。
学習理論に基づいている。
 遺伝子との関連性が想定されている。
遺伝子との関連性が想定されている。
 性格は、変容・成長すると想定している。
性格は、変容・成長すると想定している。
 多くの精神疾患との関連性が想定されている。
多くの精神疾患との関連性が想定されている。
 結婚・犯罪等、人間の生活と性格との関わりを明確にできる。
結婚・犯罪等、人間の生活と性格との関わりを明確にできる。
7次元モデルは、パーソナリティ(人格)の構成概念を気質と性格に分けて、気質4次元と性格3次元を想定しています。
気質が性格の発達(自己洞察学習行動)を動機づけますが、それによって性格が変容し、性格が気質を調節します。
このように、パーソナリティは気質と性格が相互に影響し合って発達すると考えらます。
気質(temperament)とは遺伝性の人格の要素で、幼年期の経験によってその人独特なシステムが構成され、比較的安定した(変わりにくい)人格の一部として機能します。
気質の4次元 遺伝的な影響を強く受ける四つの因子
 新奇性追求 (好奇心・衝動性など)
新奇性追求 (好奇心・衝動性など)
 損害回避 (心配性・慎重)
損害回避 (心配性・慎重)
 報酬依存 (人情家・感傷的)
報酬依存 (人情家・感傷的)
 固執 (粘り強さ)
固執 (粘り強さ)
性格(charactor)とは、自らの意思で創り出すもので、自己概念(自分がどんな人間であるかということについていだいている考え)について洞察学習をすることによって成人期に成熟し、自己や社会の有効性に影響する人格の要素であると想定されています。
性格の3次元 環境的な影響を強く受ける三つの因子
 自己志向性 (自尊心・自分への信頼感)
自己志向性 (自尊心・自分への信頼感)
 協調性
協調性
 自己超越性 (スピリチュアリティ)
自己超越性 (スピリチュアリティ)
クロニンジャー理論では、「性格」が十分に発達していなくて未熟だったり、強いストレスがかかったりしたときに、それぞれのタイプの人が、パーソナリティ障害になりやすいと考えています。
DSM-Ⅳでは、全部で10種類のパターンを想定していますが、クロニンジャーの気質の組み合わせで、この10のうち7つを説明できると考えています。
心理学では色々な性格論があります。
その一つを紹介します。
ロバート・クロニンジャーの「気質と性格の7次元モデル」
ロバート・クロニンジャー(Robert Cloninger)は1944年生まれの精神科医で遺伝学者。
1996年にネズミの行動パターンの研究から構築された「気質と性格の7次元モデル」を提唱しました。
遺伝子や脳機能と「性格」を関連付けた最新の理論です。
パーソナリティ形成では遺伝的要素も強い影響を与えると提唱し、遺伝子構造が脳内の神経伝達物質、とりわけ受容体の働きや個数に影響を与え、行動をも左右するとしました。
特徴
 学習理論に基づいている。
学習理論に基づいている。 遺伝子との関連性が想定されている。
遺伝子との関連性が想定されている。 性格は、変容・成長すると想定している。
性格は、変容・成長すると想定している。 多くの精神疾患との関連性が想定されている。
多くの精神疾患との関連性が想定されている。 結婚・犯罪等、人間の生活と性格との関わりを明確にできる。
結婚・犯罪等、人間の生活と性格との関わりを明確にできる。7次元モデルは、パーソナリティ(人格)の構成概念を気質と性格に分けて、気質4次元と性格3次元を想定しています。
気質が性格の発達(自己洞察学習行動)を動機づけますが、それによって性格が変容し、性格が気質を調節します。
このように、パーソナリティは気質と性格が相互に影響し合って発達すると考えらます。
気質(temperament)とは遺伝性の人格の要素で、幼年期の経験によってその人独特なシステムが構成され、比較的安定した(変わりにくい)人格の一部として機能します。
気質の4次元 遺伝的な影響を強く受ける四つの因子
 新奇性追求 (好奇心・衝動性など)
新奇性追求 (好奇心・衝動性など) 損害回避 (心配性・慎重)
損害回避 (心配性・慎重) 報酬依存 (人情家・感傷的)
報酬依存 (人情家・感傷的) 固執 (粘り強さ)
固執 (粘り強さ)性格(charactor)とは、自らの意思で創り出すもので、自己概念(自分がどんな人間であるかということについていだいている考え)について洞察学習をすることによって成人期に成熟し、自己や社会の有効性に影響する人格の要素であると想定されています。
性格の3次元 環境的な影響を強く受ける三つの因子
 自己志向性 (自尊心・自分への信頼感)
自己志向性 (自尊心・自分への信頼感) 協調性
協調性 自己超越性 (スピリチュアリティ)
自己超越性 (スピリチュアリティ) クロニンジャー理論では、「性格」が十分に発達していなくて未熟だったり、強いストレスがかかったりしたときに、それぞれのタイプの人が、パーソナリティ障害になりやすいと考えています。
DSM-Ⅳでは、全部で10種類のパターンを想定していますが、クロニンジャーの気質の組み合わせで、この10のうち7つを説明できると考えています。
Posted by Mako Takabayashi at 22:53│Comments(0)
│カウンセリング